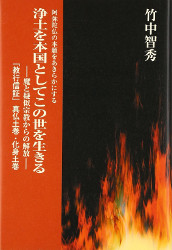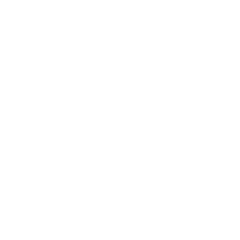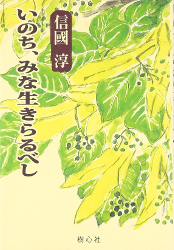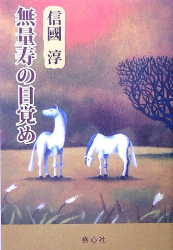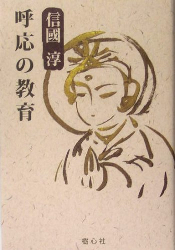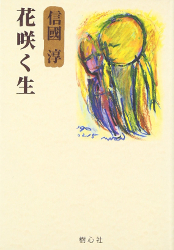| 青草びとの会・学習会の目的 | 青草びとの会の歩み | 奨学金制度 | 事務局について |
■生い立ち
●1969年1月「同窓生学習会」発足
学院の機関紙の『願生』を見てみますと、専修学院の同窓生たちはおりにふれて学院へ顔を出したり、
学院祭(現・願生会)では同窓生大会が行われたりしてきました。
また1963(昭和38)年ごろから、各地の有志によって聞法会(夏期講座)なども開かれてきました。
そうした動きを受けて、1968(昭和43)年に、同窓会を作ろうという声が涌きおこり、準備をかさねた上で、
翌1969(昭和44)年1月18日に、各地の代表者が集まって、同窓会が発足しました。
そのおり信國 淳先生の、”専修学院の同窓会は学習するものであってほしい”という教えに従って、
「同窓生学習会」という名告りをあげたのだと聞いています。
■スクーリング
●1970年2月から「スクーリング(2泊3日の合宿研修会)」毎年開催
同窓生学習会発足のひとつの大きな願いは、スクーリングをもちたいということでした。
それまでにも、各地の同窓生によって夏期講座などの聞法会などが開かれていましたが、
そうした現場での学びをお互いが持ち寄って、年に一度、学院にあい集って、聞法学習の
場を開きたいという願いが熟してきたのです。
それで、1970(昭和45)年2月5日から9日にかけて、第一回のスクーリングが開催されました。
同窓生の現場での課題を集約した「業火の中で」という統一テーマをかかげて、
信國先生に『正信偈』を講義していただきました。
スクーリングは毎年2月の後期修練の期間中に行われてきましたが、1981(昭和56)年に、
学院が山科と岡崎の二学舎になった関係で、翌年から8月の下旬に開催するようになりました。
以来、長川一雄先生、笠原保寿先生、竹中智秀先生、狐野秀存先生と歴代院長の講義を受けながら
続いてゆき、2016年山科に大谷専修学院新校舎ができてからは、毎年7月中旬に同学院で開催されています。
■夏期講座
●自主発生的に起こった「夏季講座」
1965(昭和40)年ごろから、各地の同窓生が思い立って、夏期講座が開かれるようになりました。
信國先生はじめ、学院に縁をむすばれた先生がたの講義を受けました。そうした夏期講座を
きっかけに、日ごろの生活を通しての学びを確かめ、また互いに語りあう、学習会の場が
広がっていきました。
■キャラバン
●全国各地での学習会「キャラバン」
同窓生学習会の活動のもう一つの柱として、ずっとつづけられてきたのがキャラバンです。
事務局のものが手分けして、各地の同窓生のところを回り、生活現場での声に耳をかたむけて、
それを機関紙上に報告します。
学院では一緒に学ぶ友達もいますが、地方に帰りますと、一人ひとりの生活の場におこってくる
さまざまな問題をかかえながら、ぽつんとひとり耐えている人もけっして少なくありません。
そのような「地の塩(注1)」となって聞法しておられる人たちの
声なき声が聞こえてくる場として、
学習会が公開されていくことを願って、キャラバンが行われています。
※注1:「地の塩」=新約聖書・マタイ福音書より、「優れたもの、役に立つものを示す比喩から、
人知れず世の中を支えている人々を意味する」
■出版
●様々なスクーリング・夏期講座関連の書籍を出版
最初は、1970(昭和45)年の第一回スクーリングを終えて、その記録を本にしようと思いたちました。
当時は、前の年の4月に「開申(かいしん)(注2)」が出て、真宗大谷派における、いわゆる教団問題が
沸騰していました。
午前は信國先生の「正信偈」の講義を受けて、午後に考究し、夜は教団問題の渦中にあって否応なく
問われだした自分のありかたについて、時を忘れて語り明かしました。
※注2:1969年、前門首大谷光暢氏が兼務していた法主・本願寺住職・管長のうち、管長職だけを
長男光紹新門に譲ると発表した事を開申という。 開申事件を契機に、教義解釈や宗派運営の方針、
財産問題等を巡り、改革派が主導する真宗大谷派内局と法主派との紛争が始まった。
そうした当時の状況がはらんでいた混沌とした熱情の中で、その根を押えて信國先生は「聞佛説法」と
いう一事を教えられました。
「佛の説法を聞くという自己のみが歴史を荷負い、社会を荷負う自己を我々の中に生み出す」
と語られました。
そのスクーリングの記録を『正信偈講義』として出版したのです。
それ以降、スクーリングの講義録を中心として何点かの本を出版してきました。
また各地の夏期講座の記録もいくつか、主催の学習会と協力しながら小冊子にしてまいりました。
そして1999年には遂に数年来の課題であった竹中先生の『正信偈(依釈文)講義録』を出版しました。
その後、広く一般に手に取っていただける書物の刊行を願って、
2005年『新編 信國淳 選集』(全五巻)、
2006~2007年『教行信証講義』(全三巻)
2015~2016年『竹中智秀選集』(全八巻)
を出版しました。
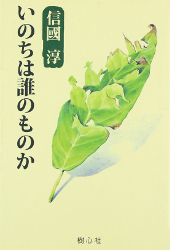 |
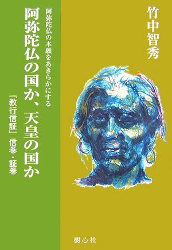 |
 |
■出版物購入方法
各タイトルのamazonマークをクリックすると、該当本購入ページにリンクします。
●信國淳・元学院長「新編 信國淳 選集」(全五巻/各刊¥2,160)
「いのちは誰のものか」![]()
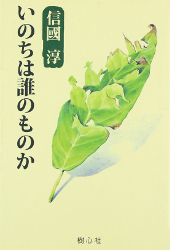
●竹中智秀・元学院長「教行信証 講義」~阿弥陀仏の本願を明らかにする~(全三巻/各刊¥2,808)
「阿弥陀仏の国か、天皇の国か―『教行信証』信巻・証巻」![]()
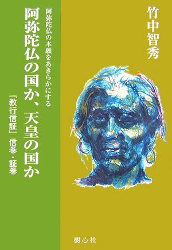
「浄土を本国としてこの世を生きる 阿弥陀仏の本願をあきらかにする-魔と擬似宗教からの解放-
『教行信証』真仏土巻・化身土巻」![]()